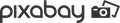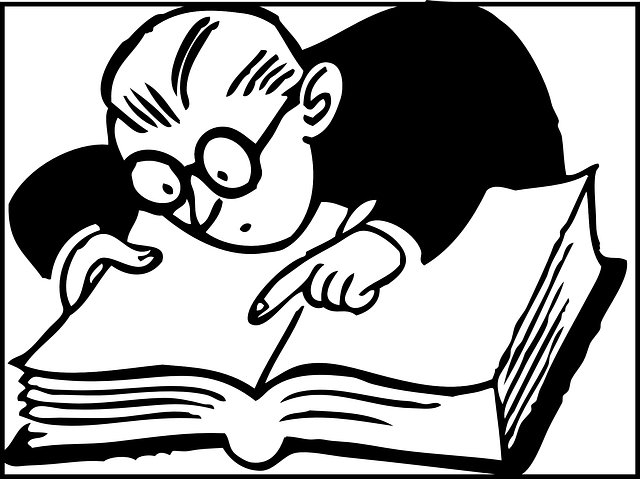「賞味期限」と「消費期限」の違いとは?意味や使い方を解説!
「賞味期限」と「消費期限」の違いについて解説していきます。同じような言葉ですが、それぞれ意味や使い方に違いが存在します。今回は「賞味期限」と「消費期限」の違いや使い方についてご紹介します。ぜひ参考にしてみてください!
「賞味期限」と「消費期限」
「賞味期限」とは、「開封せずに決められた方法で食品を保存した場合においしく食べれられることができる期限」のことです。
日本農林規格の規定に基づいて、期限がある程度過ぎていても品質は劣化していきますが消費期限とは違い、かんぜんに食べられなくなる訳ではなく期限内であればおいしく食べられることが保証された期限のことです。
消費期限と違い、期限が多少過ぎていても問題なく食べられるという意味があります。
「消費期限」とは、「開封せずに決められた方法で食品を保存した場合に、品質の劣化に伴い安全性に問題がないと認められる期限」のことです。
基本的にその期限を超えてしまうと食べない方が良いとされています。
賞味期限と同様に、日本農林規格にて期限の表示が義務付けられており、賞味期限と違っておよそ5日以内にて品質が腐敗や劣化に伴い衛生上のもんだいが発生しないと決められている期限のことを指します。
つまり、賞味期限と違い、ある程度の期限内で食べれられる事が必要となります。
「賞味期限」の意味
「賞味期限」の意味として、「賞味期限の終わりや賞味期限の終わりの日時」と言った意味があります。
劣化が比較的遅い食料品をそのままの状態で所定の状態にて製造者が安全性や味・風味など全ての品質が保持されると保証する「期限の終わりの日時」のことです。
衛生面より品質が重要なので衛生的に長期保存できる加工食品に食品衛生法に基づき一律、「賞味期限」と記載されています。
「消費期限」の意味
「消費期限」とは、食品を初めとする物品の商品期限の表示の一種といった意味があります。
商品の安全な消費する期限の終わり、すなわち安全な消費する期間のおわりの日時を表示したものになります。
食品の消費期限は、食品衛生法での安全性注意が特に必要な生鮮食品や加工食品に対して設定している場合が多く、おおむね5日以内に品質が低下する食料品には食品衛生法に基づいて「消費期限」と記載されています。
「賞味期限」と「消費期限」の違い
「賞味期限」と「消費期限」の大きな違いは「食べることが可能な期間」です。
「賞味期限」は、袋や容器をそのままの状態で、記載された保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで保存できます。消費期限と違い、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」のことです。
「消費期限」とは、袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合にこの「年月日」まで保存できます。賞味期限と違い「安全に食べられる期限」のことです。
「賞味期限」と「消費期限」を使った例文
最後に「賞味期限」と「消費期限」を使った例文をご紹介していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
例文
- 例文 食品を買ったときは「賞味期限」を確認しよう。
- 例文 生鮮食品を買った時は、「消費期限」を守って料理しよう。